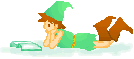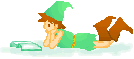|
平成15年、今年は大物の引き際に係るニュースが多かった。勿論、大物とは、各界の重鎮であり、組織のトップやトップを経験した者である。そうした人達の各界からの引退は、依願退職や定年退職というようなケースは少なく、後進に道を預け自ら退く勇退という形が多い。
旧海軍では「将は、自ら辞す」として慣行化していたと聞くが、現在の海上自衛隊でもその伝統を継承し、何かに直面した重大な情勢下でない限り、余人を以って代え難しというケースは殆どなく、概ね勇退が淡々と続いていると私は認識しており、良い慣行、伝統と考えている。 勿論、退いた後は求められない時を除き、意見を送らずという姿勢を基本とするとされている。この姿勢についても、私自身の長い勤務経験から至当と考えている。一般に後進は、現在の情勢に対応する十分な能力を有しているからである。
標題の「秋」は、「とき」と読む。ちょっと脇道に入るが英語の辞書で秋に相当する「autumn」と「fall」を調べてみたが、「時」と言う意味を見出すことはできなかった。やはり、この秋を「とき」と読み、それも重大な局面などの「とき」を意味するのは、日本古来の農業の中で「秋は穫り入れの大事な時」として醸成された文化的遺産でもあると考える。こうした意味において、標題を「引き際の秋」と題した。
話は、元に戻る。将来を見通すには、過去を見よ、50年先なら過去50年を、100年先なら過去100年を見よという。過去、つまり歴史とは、人により作られた経過であり、その時の価値観と情勢の下、人が理性で、ある時は感性で舵をとった航跡である。その時の体制が、独裁的なものであれば、ややもすれば感性が強く作用し、理性を失った舵取りだって多くある。
しかし、国政では、リーダーが人智を寄せ、国益のための最大公約数を採用しているのが一般である。したがって、歴史が、人そのものが大きく変わらない人間により作られている歴史であるが故に、同じ成功、失敗を繰り返しているのが現実である。
平成9年の秋、毎年恒例の奈良正倉院収納品の展示に足を運んだことがある。展示品は、当時の住民の登録と納税に関するものがあり、これらの資料を読みながら、知識は進展するが、人の知恵は、昔も今も一緒である、人そのものは、本当に変わらないものと考えたことを思い出す。
ということを前提とすれば、より長い人生を経験した者としては、人の原点にかかるようなこと、民族と文化、その生活様式と思考様式に係ること、人間の生き抜くための闘争を含む活動など等、世界の流れをマクロ的に見た、つまり長い歴史から導き出される冷厳な世界の現実を正確に伝えることぐらいが、毎日が多忙な後進へ積極的に進言することかも知れない。
私の他のコラムにも良く述べていることであるが、理論的には、人類は個人、家族、部族、民族、国家、世界国家という単位で生存できる中で、敢えて有史以来、数千年以上に亘り「国家」というグループ単位を選択し、幸福を追求してきている。
この幸福の追求は、生きる、暮らす、より豊かに暮らすという物理的側面と、価値観・文化・主義という精神面での満足さを求める形でなされてきている。こうした中、個人から国家単位へ辿りつく過程において、グル−プ内の秩序を保つため、共通の価値観(文化)の下、人としての倫理(人間的道義)、人同士の約束事、グループの掟、道徳(社会的道義)、法という仲間の規則・制度が確立された。つまり、人が社会的責任を取るべき道義から強制力を伴う刑というものまでが秩序を維持する手段として出来上がったと考えられる。
本来、こうした制度は、人間的道義がしっかり確立していれば、社会的道義や、ましてや醜い強制力を伴う「法」は、この世の中に不要なものであっただろう。無法の法という言葉があるが、人間は、自然に生まれ備わっている法則で、本来は秩序正しく協同生活をできなければならないのである。しかし、人間社会でそうした理想的な状態となっていないのは残念である。
勿論、だからと言って、「仕方なし」の一言で放り出せるものではない。
海上自衛隊での経験を通じ、感じたことがある。当然民間の組織の中でも言える事とは思うが、身の危険、生命を預かることにより任務の達成が為し得る自衛隊という社会では、若くして幹部に据えられたが故に、明瞭に感じたのかもしれない。
それは、結論を先に述べれば、次のとおりである。
部下を率いるには、
一つ、初級士官は、体、知、智、徳のうち、主として体力で率いる。
一つ、中級士官は、体、知、智、徳のうち、主として知力で率いる。
一つ、上級士官は、体、知、智、徳のうち、主として智力で率いる。
一つ、高級士官は、体、知、智、徳のうち、主として徳力で率いる。
ということである。
つまり、組織のトップに近い立場にある者ほど、「徳力」で、組織を率いるのである。それは、何故か? それは、「人」は、身を賭けるようなとき、良く知っているから、理性で承知しているから自発的に動くのではなく、上司に感じて動くからである。
理解すれば、知れば動くという「理動とか知動」という言葉はなく、感じて動くという「感動」と言う言葉はある。組織は、上級者の言葉ではなく、その姿勢に感じ納得して正常に自ら動くのである。
「部下は、常に後ろから上司の背中、つまり姿勢を見ている。」という旨の言葉を残した大先輩がいるが、若輩者が言うには僭越であるが、正しく同感である。
西郷隆盛、鹿児島に在って話題となると、日本の近代化を為し、列強の侵略から我が国を守った大久保利通より、遥かに高く大人物として評価されている。それは、何故だろう。
司馬遼太郎の「街道を行く」の一節に書かれていたと記憶しているが、南の島々から鹿児島、土佐、紀州の黒潮流域には、村々の行事や災害対処においては、青年団が仕切る、采配するという慣習があったという。明治の維新政府が、中央集権国家の確立に阻害する要因として捉え、その弱体化に神経を使ったぐらいである。
そのような慣習が根強く残る鹿児島において、征韓論に破れ鹿児島に下野した・・・というより、多分に西郷の西洋に対する認識からすれば、米国・西洋視察の岩倉使節団に参加し帰国した大久保の「欧米脅威論」が正しいと判断し、政府中枢から身を引いた・・・西郷が、私学校の青年の御輿に、「そうか、わしの命をくれてやろう。」といって命を預けて乗ったとされる。
西南の役の経緯に目を転じてみよう。西郷の知識、能力からすれば、陸路をとるよりも海路を利用し、他の味方勢力を合流させ、上京する・・・これが、至当ではないだろうか。にも拘わらず、最も困難な陸路を選んで、結局、若しかしたら意図的に、自滅の道を辿る。
政府の中央まで上り詰めた西郷が、どう引き際を考えたのだろう。自ら辞したのは明瞭であるが、それだけではなく、自分が命を永らえた場合、後進の舵取りへの悪影響までも考えたのではないかと私には思える。
日本文化は、本来、美醜の文化であると言う人がいる。自然との調和の中で協力し合って頑張れば生存の為の糧が得られ、一年が安心して暮らせるという自然条件に恵まれた日本では、人との協調や人を不愉快にさせない行為を良いこととした。こうした良い行いを美しい行為とし、そうでない行為を醜い行為とした。こうした善悪の物差しを美醜の文化と言う。
話は少し横道に入るが、この夏、ある本の中に、「現在、稲は、一粒の米から一本の苗となり、植えた後七本に枝分かれし、それらの一本に270粒が付く。合計1,890粒の米が穫れる。」と言う記事があった。これを前提に、定住稲作が始まった弥生時代の収穫がどれだけあったかを考える。少し乱暴であるが、品種や肥料などを考慮し10分の1とすると、1粒の米から約190粒が穫れたことになる。
世界に目を移すと、中世のヨーロッパで、1粒の麦から6粒程度、グ〜ンと遡って土地の豊かさから四大文明の一つとなったメソポタミアでは、1粒の麦から約72粒という記録が残されている。 日本の稲作での豊かさが目立っていると私は考える。
こうした日本の自然の豊かさは、「仲良くやれば、和を保てば」という条件付ながら、豊かな、優しい、温和な精神を醸成し、悪者を段階をつけて罰する律令、つまり法の制度までが優しく、集団の秩序を「美」という概念、つまり、人としての、社会人としての道義心をもって秩序を維持しようとした。厳しい環境条件での法、契約社会、そして厳しい戒律の宗教で成り立つ外国と、甘い法と優しさを原点とする仏教で成り立つ日本、この差は、読者には明瞭に映らないだろうか。現在は、かなり文化までが欧米化した日本だが・・・・。
日本に「村八分」という言葉がある。日本人としては、無視する、のけ者にするというこの言葉をかなり厳しい、ひどい行為と解釈するものが多いと思う。しかし、余りにも非常識、非協力的で在るが故に、八分は仲間として認めない、とは言え、「家事」、「死者の発生」という予期せぬ緊急事態の二分については仲間として認め、協力する。生命を度々賭して生き抜いてきた欧米社会に比べれば、優しいように感じる。 読者の方はどう思いますか。
こうだからと言って、日本人が鈍感であるのではない。結構繊細で、機微なセンスを持っているのも日本人である。多くの例を挙げられると思うが、そのうち、少々。
中国では、季節の節は12と聞く。日本では、24であるそうだ。季節変化の速さと農作の準備や作業がこうした区分を否応無く感じさせたのかもしれないが、情感の豊かさ故のものでもある。
また、良い例ではないかもしれないが、江戸人の色の表現として、「百鼠四十八茶」という表現がある。読んで字義のとおり、百種類のねずみ色と48の茶色となる。ねずみ色では、限りなく白から限りなく黒までのねずみ色なのだが、白鼠(しろねず)、薄鼠(うすねず)から始まって、桜鼠、藤鼠、茶鼠、利休鼠(北原白秋の城ヶ島の歌で有名)、濃鼠と百種類となるそうである。物理的な表現から、文化的表現までが混在しているところは、日本人の侘び、寂び、渋さの文化故の言葉ではなかろうか。
この秋話題となった引退劇は、藤井道路公団総裁と中曽根元総理大臣が挙げられる。
藤井総裁については、特に印象に残る経緯として、「人生国土交通省一筋と官僚最高位の事務次官」、「財務諸表と国会答弁」、「国交省は全て了解、死人が出る、私は薩摩人発言」、「聴聞と弁護人」、「週刊誌への実名発言」など等あるが、私をがっかりさせたものは、「省も了解している。」「他に絡んでいるものがいる。」「薩摩人」「弁護士代理人」の言動である。本当の真実は、私として勿論知るべくもないが、こうした言動が高官によってなされたことである。
また、続いて、中曽根元総理の言動である。 私にとっては、元総理が旧海軍士官と言う先輩であり、語りたくないところであるが、「終身議員は、党との約束」という考えの発言が気になった。
標題に、「引き際」を掲げたので、読者は、上記の事象を思い浮かべ「高官の退き方はいかにあるべきか。」という疑問符をもって読んで頂いたに違いないと思う。
私は、一言でいえば、「高官は、自ら情勢を判断し進退を決める。」べしと言いたい。
少し、私の感想、考え方を示しつつ、細部に言及してみたい。
「他もこれを了解、また絡んでいる。」というが、ではこれが、何か更迭撤回の理由になるかということである。私としては、高官の反論としては、全く次元の低い理由にしか見えない。
数年前の現役の時代であったが、その5年位前に部下だった某幹部から、「私も処分を受けることになり覚悟はしていたが、何故自分だけが、まるで代表者のように罰せられなければならないのか疑問を感じ出した。」という電話相談が舞い込んだ。「私は、他の者はどうであれ、自分が正当でなかったと自分で感じるのであれば、それに対する処分は、甘んじて受けなければならない。他の者が、同罪となったとしても、君の精神的呵責が消えるわけではないだろう。」と答え、彼は納得した。
ましてや高官であれば、法的には触れないとしても、不善の行為であり、恥ずべき行為と感じていれば、自己を自身で処するべきと考える。 他(省)が了解していたとしても、説明したのは、自分であり、それが不善であったと考えられれば、省の了解には関係なく、自身の不善行為に変わりは無い。省は省としての問題と捉えればよい。
また、「薩摩人出身・・・」。 なんでもない人までもが不愉快になる言行は、控えて欲しい。西郷隆盛が泣くよと感ぜずにはおられなかった。
「弁護士代理人」の出現。これが、一番私をがっかりさせた行為であった。この後、彼の代理人の名誉毀損などの発言もあるが、彼は、自分が高官であると言う立場において一体何を考えているのだろうと溜息を吐いた次第である。
日本は確かに法治国家であり、人は一応法を犯さなければ、罪を受けることはないだろう。しかし、今までも法には触れない事象であっても、「社会的責任」とか、「立場上の辞職」などという言葉は、数限りなく聞いてきている。
前述したが、世の中は、人間は人間としての倫理に反すれば、また、社会人は社会的道義に反すれば、社会的責任を取ることになる。更に、法を犯せば、当然のことながら罪を受けることになる。
人間は、特に社会的に組織的に高い位置にある者は、法は犯さなくとも、一般人では社会的責任が生じない小事であっても、社会的責任、人間としての責任を追及される。
世を率いる立場にある者の必然的責任である。 こうした意味から、弁護人を表に出す、つまり、法的範囲で勝負をするという姿勢に私は、唖然としたのであった。
初級、中級の官僚であれば多分唖然としなかっただろう。何故ならば、下方の官僚ほど法に忠実に、規則に従って職務を遂行するのが大原則であるからである。繰り返すことになるが、彼が「法」と言う概念の範囲のみで判断しようとすることは不適切と思わざるを得ない。
高官は、勿論それに準ずる者も、自ら情勢を判断し、大局的視点に立って、自らを含めて処置することが大切である。「知識、見識、胆識」という言葉がある。見識までは、その文化、哲学が異なれば多分議論にまで亘ることになるであろう。しかし、それでは処することが出来ないこともある。私的立場を離れるのは当然、国家的、組織的により高い視点をもって判断する、それが胆識をもって処するということである。
先の大戦においての話であるが、ミッドウェイ作戦に従事した空母飛竜の話である。海戦で武装転換中に米軍の航空攻撃を受け、赤城、加賀、蒼竜が撃沈され、最後に残った空母飛竜は、単艦、指揮官山口多門海軍少将指揮の下反撃するなど奮戦するが、遂に被弾し艦を救って帰港すべしかを考えるが、火勢が大きくなり、遂に離艦を決意するに至る。この間、再々の艦内捜索を行い負傷者を含め乗員の駆逐艦への収容も図るが、公式戦史の記述とは異なり、使命感に燃え無傷ながら配置を離れようとしないものも散在していたと言う。しかし、時間をかけすぎた処置は、米軍の更なる攻撃を受け、残留し護衛に当たっていた駆逐艦など味方部隊の被害を大きくしてしまうのではないかという状況下に陥ってしまった。
山口司令官は、こうした艦内生存者がいることをも承知しつつ、加来艦長と共に艦橋に残り、味方駆逐艦に今や漂流している空母飛竜に雷撃を命じ、生存している部下及び艦と運命を共にした。司令官なりの責任の取り方である。
部下を如何に確実に救うか、味方損害をどう局限するか、国家の為にいずれを選択すべしかという葛藤があったものと思う。正しく胆識をもっての判断であっただろうと思えてならない。
「指揮官は、孤独である。」と言う言葉があるが、最後は、自分独りで決心しなければならないのである。
高官、勿論経済界など各界を通じての話であるが、指導者の立場にあるもの、高官は、国民に模範を示すべき立場にある。その言行は、一挙手一投足まで国民によって見守られているのであり、その言行そのものが、国民に対する教育と捉えても過言ではない。
人生72歳を全うし、世に多くの言葉残した孔子、人生の後半について、五十にして天命を知り、六十にして耳順い、七十にして己の欲するところに従い、矩を踰えずと人の生き方と生き様を示している。 五十で世の中の自己の位置づけを悟って、世に貢献し、六十にして他人の言うことに耳を傾け、そして最後は自分が思うまま勝手に行動するが、世の基準を踏み外すことは無いと言っているのだろう。
「自律、自立、他律」という言葉がある。これらに甚だ勝手であるが、造語「他立」を加えて整理すると、人生は、若い頃は、他律によって自立させられ、熟しては、自律しつつ、他立させられているような気がする。人生、誰しも最後は自律を軸として世を渡るべきである。
法のみが、世の中の尺度でないと再認識した出来事であった。
旧ソ連時代に国外に亡命したチェロリストがいた。彼は、「人間は、二つの裁きを受ける。一つは、法、道義と言う外からの裁き、一つは、自分の良心による裁きである。」と述べており、当時、ソ連の教育は素晴らしい、日本はどうだろうと考えたことがある。
日本にも、臨済宗禅の教えに、「無位真人」という言葉がある。それは、「自分の人格は三つある。己が見る自分、他人が見る自分、そして自分を離れ公平無私な自分がある。」としている。
人間は、誰しも良い心と悪い心が同居していると思う。ふと湧く悪い心を許容して導く胸の広さが大事である。
不善と気付いた時、引き返す勇気が必要と思う。こうした心構えを国民皆が持つには、家族、学校、地域社会のみでは達成し得ないだろう。国を挙げての教育、感化の活動が要るのだろう。
(終わり) 海翔
|